
塾長の考え(ラジオ番組名)
昨日お邪魔させてもらったラジオ番組名は、 「Radio Leader’s」 Radio Leader’s ...

昨日お邪魔させてもらったラジオ番組名は、 「Radio Leader’s」 Radio Leader’s ...

今朝の時点で私は東京にいる。 なぜ東京にいるのか? それはラジオ放送に出演するためだ。 ...

昨日は土曜日。 2つの面談があった。 1つ目はかつての塾生で、 今は大学生(新2年生)になった生徒、 そしてそのお母...

もうすぐ3月が終わる。 明日は土曜日だが、 明後日は31日で日曜日。 4月1日は月曜日で新年度がスタート。 とはいっ...

成果を上げる学習方法と、 成果を上げない学習方法がある。 成果を上げる指導方法と、 成果を上げない指導方法がある。 ...
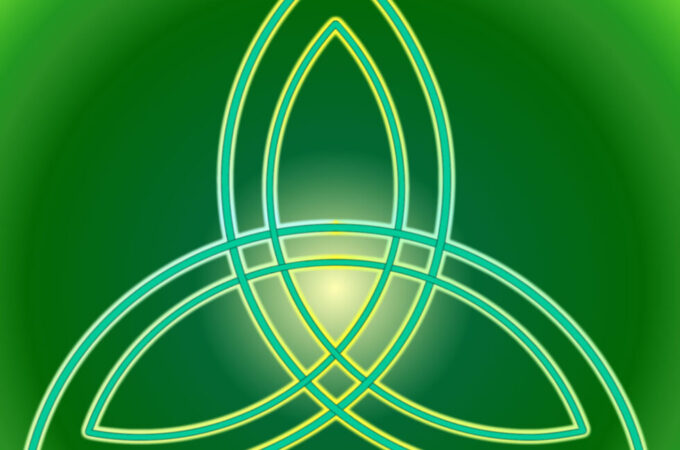
学習や勉強の「やり方」の基本は、 「理解」「記憶」「実戦」、 この「学習構造3要素」、 この順番を守ること。 さらに...

先日の祝日。 出張で大阪に行った。 この出張で極めて重要な情報が、 手に入った。 これが...

「九大の過去問をしたいです」 「ちょっと待って」 「はい」 「これを…」 「ふ~ん、ココからやるんだ…」 ...

次は、 「どのように」 になるのだが、 たくさんの学習塾があるけれど、 勉強のやり方を教えていない塾が、 ほとんどのようだ。 &n...

「合格しました」 という電話での報告があった。 中3の生徒から。 まあこういうケースもある。 「ありが...